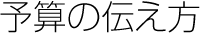ウェブ制作会社のマッチングデータベース

ウェブ制作会社の
探し方 
 Webサイト制作を依頼するには
Webサイト制作を依頼するには
 小さい工務店は大型ビルを造れない
小さい工務店は大型ビルを造れない
Webサイトを作ることは、建物を建てることに似ています。
建物の場合、利用規模によって様々なものがあります。
2〜3人で住むための1階建ての住宅もあれば、数百人が利用するオフィスビル、
さらにはたくさんの人が集まる、巨大なタワー群を擁する複合施設まで、
規模はピンからキリまであるでしょう。
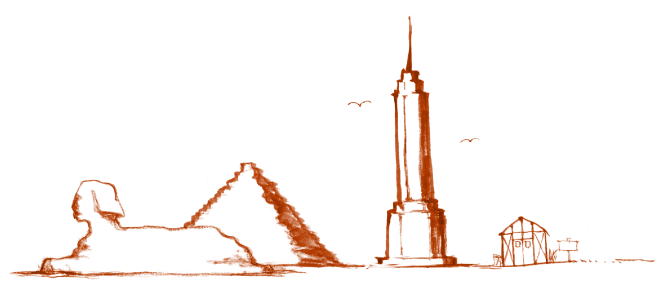
Webサイトは、言ってみれば仮想建築物のようなものです。1日数人が見る個人サイトのようなものから、世界中で莫大な人数がアクセスするサイトまで、一口に「Webサイトを作る」と言っても、利用の仕方によって、大小様々な可能性があります。
こういった前提を理解しないまま業者探しを始めたとしても、なかなかうまくいきづらいのが現状です。地方の工務店に「六本木ヒルズ造って!」と言っても無茶ですし、大手ゼネコンに「小さいプレハブ住宅を建てて!」と言っても限りなくミスマッチなのは想像できますね。
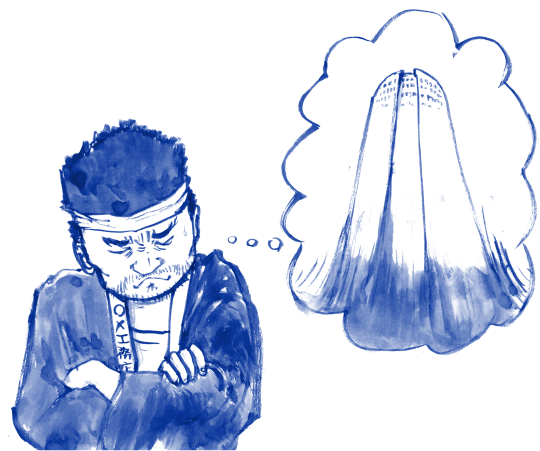
 Web制作の「はじめの一歩」
Web制作の「はじめの一歩」
つまり、目的に合ったWebサイトを作るには、
その目的に合った制作会社にアプローチすることがはじめの一歩になるわけです。
ここをしっかり押さえておけば、ある程度制作会社任せにしても、そんなに大きなずれは発生しません。
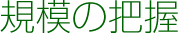
詳しくは後で説明しますが、目的とマッチングさせるには、何より規模の認識が重要です。それは予算ともイコールですが、大規模か、中規模か、小規模か、そこの認識がきちんと持てれば、成功はとても近くなります。それには大規模とはどんなものか、どういう金額規模か、ということを知らなくてはいけません。
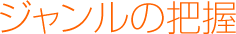
規模以外には、ジャンルも重要な要素です。ECサイトを作りたい人が、広告キャンペーンなどを専門に手がける会社にアプローチしてもマッチングしづらいですね。つまり、自分が作りたいものがどんなジャンルで、何をポイントに選べば良いかを理解すれば、ほぼ失敗することはないでしょう。
 業界のルールを守れば嫌われない
業界のルールを守れば嫌われない
また、それなりに重要なのが、業界の暗黙のルールを知ることです。業界では、プロ同士のやりとりも多いので、「言われなくても当たり前」ということも結構あります。最低限の予備知識もなく見積もり依頼などをしてしまうと、どこからもそっぽを向かれてしまい、仕事がなくて困っているあまり質の良くない会社しか相手にしてくれなくなってしまう、なんていうこともあり得ます。

 Webサイト制作の進め方
Webサイト制作の進め方
 フェーズ1: Web制作の発注先を探す
フェーズ1: Web制作の発注先を探す
発注先を探し始めるために、まずは自分たちが目指す方向性を整理しましょう。
初めに、目標のWebサイトの規模を明確にします。
 1.規模を把握する
1.規模を把握する
発注先を探し始めるために、まずは自分たちが目指す方向性を整理しましょう。
初めに、目標のWebサイトの規模を明確にします。
※規模の指標はWEB COMPASS独自の分類によります。
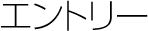
中小企業のコーポレートサイトのような、10ページ以下程度の静的なもの。いわば紙のパンフレットにお問い合わせフォームがついたようなイメージ。1日数件程度のアクセスが想定される。

ページ数が多く更新頻度が高い、商品販売する、など、ある程度の機能性が必要なもの。1日数100件程度のアクセスを想定。
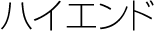
ページ数が定まらず、運用中に日々可変していく。1日数1000件程度はアクセスが想定される。
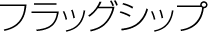
どれにも当てはまらず、もっと規模が大きいと思われる。1日10万件程度のアクセスがある、たくさんの商品を販売する、Webサイトと言うよりアプリケーショzン的、など。
 2.作りたいものの種類を明確にする
2.作りたいものの種類を明確にする
次に行うことは、種類を明確にすることです。
例えば、ざっと大きく分けると、Webサイトの種類には以下のものがあります。
会社の情報を掲載したい

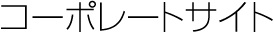
商品のプロモーションをしたい

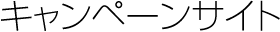
商品やサービスを販売したい

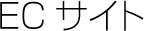
世の中に情報を伝えたい

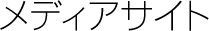
レアケースなどを考えるともっと多種多様ですが、多い目的はこれらです。細分化していくともっと細かく分かれていくわけですが、この段階では大まかなゾーンを把握していれば大丈夫です。
 3.予算とのマッチングを見る
3.予算とのマッチングを見る
1で仕分けした規模の分類ですが、この分類でざっくりとした予算ゾーンが決まります。
具体的には、

万円前後
予算規模
10万〜100万程度
万円前後
予算規模
100万〜500万程度
万円前後
予算規模
300万〜1000万程度
万円前後
予算規模
1000万円〜
このように見込めます。
もちろん、広い土地に小さい家を建てる人もいれば、狭い土地にペンシルビルを建てる人もいるので、上記のゾーンはあくまで目安です。例えばECサイトを作って商品販売をする場合に、「エントリー」の予算感では絶対に無理で、少なくとも「ミドル」ゾーンの予算は必要になりますので、その程度の照らしあわせをしつつ、そもそも制作会社に見積もり依頼をする意味があるか、をきちんと検討してください。
 4.見積もり依頼仕様書を作る
4.見積もり依頼仕様書を作る
例えば美容室で髪を切る際、店によってはスタッフの指名ができます。その際、指名料がかからない店もあれば、ランクによって金額が違う店もあります。
Webの制作についても似たような面があり、誰が担当するかによって仕上がりは確実に変わるため、お金をより出した方がスキルの高いスタッフが担当する可能性が高くなります。
予算は伝えずに見積もり依頼をした方が安い金額が出てくるのでは、と思うかもしれませんが、実際には、スキルの低い人をあてる前提で安く出しておこう、と考えて見積もりを出してくるかもしれません。安いは安いなり、ということを覚えておくとよいでしょう。
ある程度の予算ボリュームゾーンを伝えた上で、「金額を抑えるならこういうやり方」「クオリティを求めるならこういうやり方」という提案をもらった方が、結果的に満足するものに近づくように思います。本当は100万円でできるのに、予算を500万円と言ったらぼったくられた!というようなことは、健全な会社であれば起こりません。
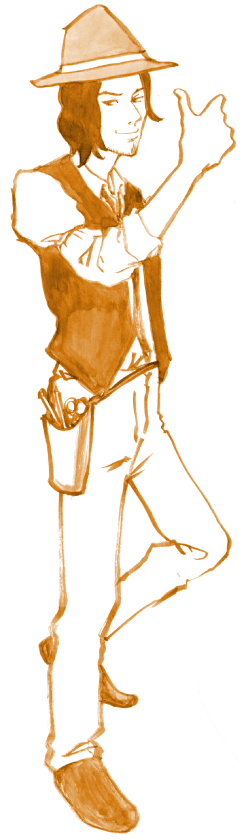
(イメージ)

(イメージ)
 5.見積もりを依頼する
5.見積もりを依頼する
仕様書に必要事項をまとめたら、実際に見積もり依頼をしてみましょう。見積もりを複数社に依頼する場合は、他の会社にも見積もりをお願いしている旨をきちんと伝えることが大切です。

複数一括見積り
顧客サイド: 選別が大変
製作会社サイド:見積りがとても大変
多くても3社程度へ見積もり依頼
※どうしても合わなければ他に追加依頼
中古車買い取り業者の見積もりサイトなどは、たくさんの業者に一括見積もりを依頼できますが、Web制作案件の場合はむやみやたらに見積もり依頼するべきではありません。理由は、
- たくさん来ても選別が大変なだけ
- 先方も見積もりにはとても手間がかかる
という2点で、簡単に言うと双方ともに辛い思いをするからです。
多くて3社程度に依頼し、そこがどうしても合わなければ他に追加依頼する、というつもりで臨むのが得策だと思います。
 6.依頼先を選別する
6.依頼先を選別する
見積もりをもらったら、選別を行います。各社から出される資料の形態もさまざまなので、選ぶのには苦労するかもしれません。疑問点などがあれば、直接それらの会社に問い合わせて確認していくことが大切です。その際、できるだけ電話で話したり、移動できる範囲であれば対面で話すのが理想です。来てもらうのも良いですが、逆に足を運んだ方が良いでしょう。相手の会社がどういう会社か、行ってみればたくさんの情報が手に入ります。例えばデザインに力を入れている会社であればエントランスの雰囲気が違いますし、いわゆるIT系と呼ばれる新しめの会社は、目新しさに注力していたりと、会社によって毛色は様々です。
最終的には、そういった会社の雰囲気やスタッフの人柄などをもとに、直感的に良いと思う会社を選択することが多く、またそういった選び方が理想的だと思います。見積もりの数字比較だけで選ぶと思わぬ落とし穴が待っているかもしれないので、注意しましょう。選別の結果、残念ながら依頼できない会社へは、きちんとその報告と見積もりしてくれたことへのお礼を必ず伝えてください。
 7. 発注する
7. 発注する
選別を終えたら、すみやかに発注手続きに入りましょう。一般的には、契約書を交わして進行します。Webサイトの制作は比較的時間がかかります。支払い条件なども決めておかないとトラブルになるので、忘れずに契約書を作成しておくことをおすすめすます。契約書の内容としては、制作については主に以下の内容を盛り込みます。
依頼事項 納期 検収 支払
また、サーバの維持管理やサポートなど、運用を依頼する場合が多いと思いますが、運用契約書は別に作成しておいた方がシンプルにまとまります。契約書の作成はどちらが行っても良いので、制作会社にドラフト作成依頼をしても構いません。
原則は、契約書の取り交わしが完了してから制作作業に入りますが、納期によっては制作フェーズの初期打ち合わせなどは並行して早々に始めてしまうこともあります。その辺はケースバイケースなので、制作会社と調整しながら進めてください。
Web制作は、建物と同じように、スタートから仕上がりまでかなり時間がかかります。半年程度は当たり前、1〜2年くらいかけて進行する案件もごく一般的です。そのため、仕事が終わったら支払えば良い、というのはちょっと難しく、1〜2ヶ月で完了する場合を除いては分割して支払いを行うことが多いので注意しましょう。スタート時、中間、公開時、という風に時間で分けることもあれば、スタート時、デザイン確定時、システム開発完了時、公開時、などのように、フェーズで分けることもあります。いずれにしても時間軸にそって複数回に分けることが一般的です。
こういった支払い条件は、必ず契約書に記載し、確認と合意をした上で進めましょう。きちんとしておけば、無用なトラブルを防ぐことができます。
 ウェブ制作会社の探し方
ウェブ制作会社の探し方